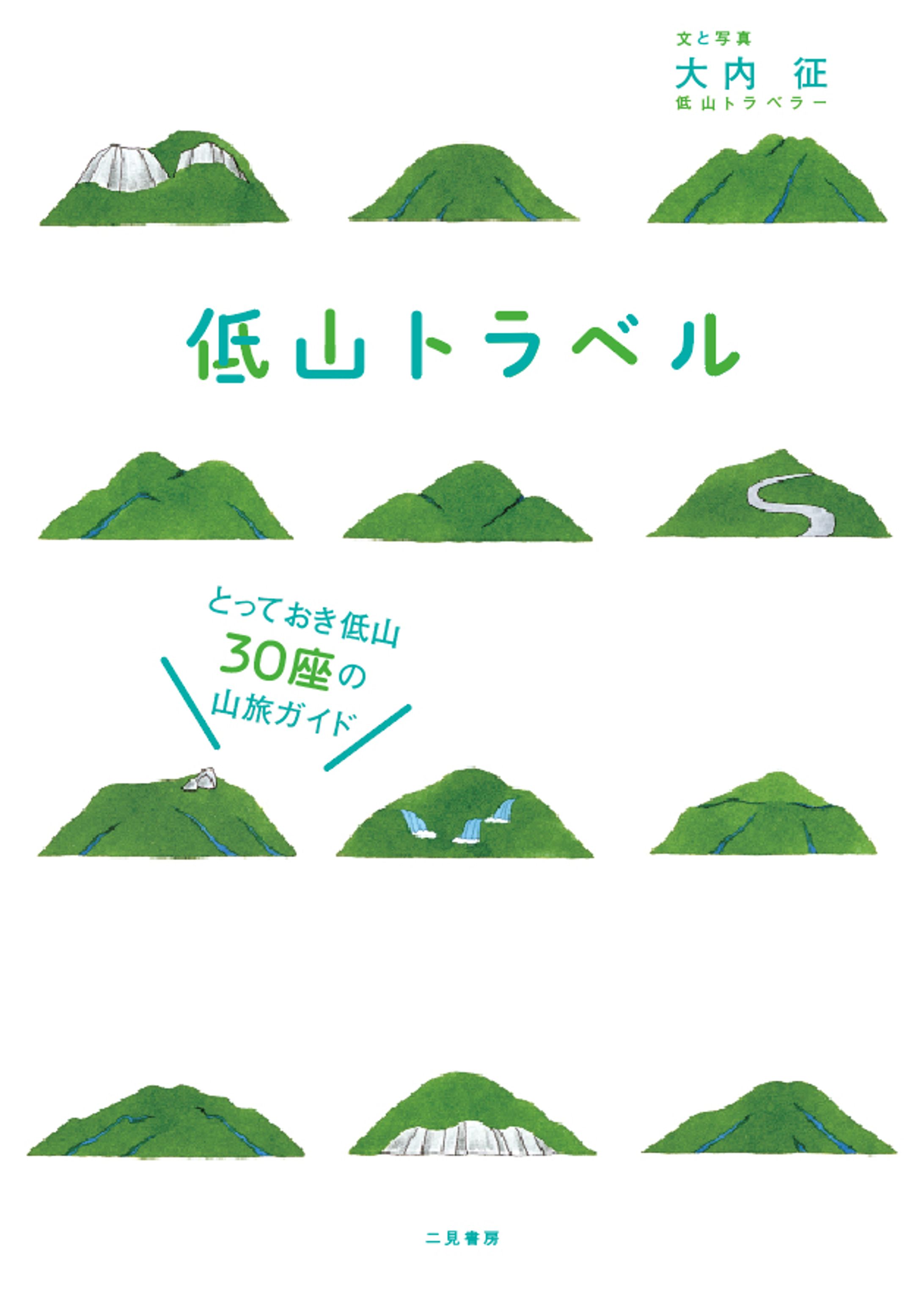クリエイターの生き方は百人百通りだ。 同じ山頂はなく、同じルートを取ることもない。
低い山に魅せられ、低山トラベラー・文筆家として活動する大内征氏のキャリアも実にユニークなものだ。登山と歴史・文化を掛け合わせた独自の論や活動を展開し、低山の楽しみを伝えている。
高く有名な山の頂を目指すことだけが登山の楽しみではないと語る大内氏は、どのようにその道を歩んできたのか。
山仲間が営むカフェ「海猫山猫」にて、これまでのキャリアや著書『低山トラベル とっておき低山30座の山旅ガイド』(以下、『低山トラベル』)に込めた想い、キャリアの展望についてうかがった。
低山が内包する歴史・文化に魅せられて
大内氏が低山と出会ったのは、30代半ばの頃。当時マーケティング系のベンチャー企業で会社員をしつつ、週末になると、東京近郊にある1000mに満たない低い山に登るようになった。
「昔から旅や自然が好きで、旅先でアクティビティとして登山を楽しんだり、南アルプスや八ヶ岳のような高い山に登ったりしていました。ただ、ある程度まとまった時間を用意しなくてはいけないので、もっと気軽に行ける山はないかと調べたんです。そこで出会ったのが低山でした。高尾山や御岳山など東京近郊にはたくさんの低山があることを知り、登り始めるようになりました」
現在では年間100座ほどの山に登り、その中の8割以上が低山だという。たとえば東京近郊にある低山の魅力を、著書の中ではこう語っている。
山に通うようになると、百名山の征服感に充たされる一方、いつしか低い山ならではの魅力が目にとまるようになりました。もともと歴史小説や寺社仏閣が好きで、戦国武将の足跡を辿ったり古いお寺を訪ねる山旅をしていましたが、里山や低山に今なお歴史が色濃く残っていることに感動し、何度も足を止めたものです(『低山トラベル』まえがきより引用)
これまでの知識や経験を活かして、いつか自分の好きなことで食べていけたらと考えていた大内氏。会社員を辞め独立するきっかけとなったのは、2011年の東日本大震災だった。 震災直後、生き方や働き方を軸とした学びの場「自由大学」にて、震災と野外活動を掛け合わせたプログラムを立ち上げたのだ。
「地元宮城の復興に向けて何かできないかと、宮城出身の仲間4人で立ち上げたのが、地域体験のプログラムです。二泊三日のキャンプ形式でフィールドワークを行い、体験を通して宮城のことを知ってもらうというものです。復旧・復興に向けてのボランティア活動ももちろん重要ですが、出身者である私は、他所からきた人たちに宮城を好きになってもらう活動をしようと考えました」
そんなプログラムを行う中、参加者に変化が現れる瞬間を目の当たりにし、大内氏は大きく心を動かされた。

「津波で被害にあった農地を借りて、キャンプをするんですね。いつもは都内でキーボードを叩いている優秀なエンジニアが、土をいじりながら『征さん、俺こっちの方が好きかも』とか言うんです。今この人めちゃめちゃ感動しているんだなーとか、泣きそうになってるなとか、ダイレクトに反応が返ってくのがすごく楽しくてね。目の前のたった一人の人生を変えられる可能性があることに面白さを感じて、そういう仕事で食べていきたいなと思ったんです」
その後約2年間は同プロジェクトの活動と会社員、二足の草鞋を履きながら働いたのち、40歳の時に独立。まず5ヶ年計画を立て、段階的に、向かうべき方向の解像度を上げ、自ら仕事を生み出していった。
「好きなことを仕事にしようとはよく言いますが、僕は、目の前にある仕事を自分が「好きなように采配を振れるようになる」ことが重要だと思っています。小さな仕事でもいいから、まずは全て自分が好きなようにやってみる。その積み重ねの先にようやく実力がつき、好きなことを仕事にできるようになるのではないかなと思うんです」
ポートフォリオを好きなもので満たす
はじめの1年間は、会社員として積んだマーケティングやWebプロデュースの経験を活かし、どんな案件も断らずに全部やることを指針とした。
2年目は、本当にやりたいこと・本領を発揮できることに集中していく。自分の中で引っかかっていた仕事や、「山」に関する仕事と遠いものは、後任を紹介したりしながら案件を見直していった。そうすることで仕事の“種まき”をする余白が生まれ、3年目以降、徐々に芽が出てきたという。
“低山に登り、歴史や文化を辿ってきた経験を活かして、低山の楽しみを多くの人に届けることに集中しようと考えました。仕事の中身を見直したことで、一時手元の案件はほとんど残らなくなり年収は半分に目減りしましたが、あのときに整理して本当に良かったと思っています”
自分が本当に取り組みたい仕事のために余白を作った結果、山やアウトドア関連イベントでの登壇やメディア出演、雑誌新聞への寄稿、NHKラジオ深夜便『旅の達人~低い山を目指せ!』のレギュラーなど、徐々にポートフォリオが好きなもので溢れるようになった。 そんな頃に舞い込んだのが『低山トラベル』の執筆の話だった。

「NHKラジオ深夜便の初回放送を聴いた二見書房の編集者の方から本を出さないかと、連絡をいただきました。本を出すことは、独立時に立てた5ヶ年計画における目標のうちのひとつ。早速きた!と思ってすぐ会いにいきましたね」
『低山トラベル』には、東京から日帰りで楽しめる低山が紹介されている。執筆にあたっては、それまで10年間撮りためてきた写真や、山を歩く中で知った物語や経験を自分の言葉で筋立てられるようにしていたことが功を奏した。
「今まで低山に登り、たまっていた知見を『低山トラベル』にわかりやすくまとめました。執筆や撮影のスキルは、会社員時代にクライアントのウェブコンテンツを作る際に培われたものが役立ちました」
本書は単なる低山ガイドブックではなく、文学作品や歴史、神話、地域などと結びついた低山の魅力が紹介されている。登山というと「山頂を目指すこと」が目的になることも多いが、他にも違った楽しみ方、視点があることを伝えているのだ。
「友達に誘われるがまま富士山に登って高山病になって痛い目にあったり、揃えた登山道具がタンスの肥やしになってしまったり、せっかく始めたのに山から縁遠くなってしまう人もいます。
もちろん山頂を目指すのも楽しみ方のひとつですが、文学や漫画、絵画などの文化作品にその山がどのように影響を与えたかを知ったり、その土地の歴史を学んだりすることができるのも、山の面白さです。「こっちもあるよね」と新しい楽しみ方を提案するのが、僕の役割かなと思っています」

本書のもう一つの特徴は、山での活動における注意点や装備、調理についてなどのコラムが掲載されていることだ。山の楽しみ方を知ってもらうだけでなく、災害時に対応するためのスキルを、楽しみながら自然と身に付けてもらえればと大内氏は語る。
「災害時には、テントを張ったり、焚き火をしたりなど、登山やアウトドアにおけるスキル・道具が役立つんです。実際に私は東日本大震災の時に、山用に用意していた水や食料、クッカーなどがそのまま備蓄として活かされました。 水や食料を備えておきましょうとか、こういうことを覚えておきましょうと言っても、人はなかなかやりません。なぜなら、災害はいつ起こるかわからない遠いものだと心のどこかで思っているから。しかし、普段からアウトドアを嗜んでいると、楽しみながら災害時のための備えにもなるんです」
文筆家から「作家」へ。街と自然の循環を紡ぎたい
『低山トラベル』のあとがきには「人里の上にたなびく低山を巡り歩けば、未知の面白さに出会」うと書かれている。大内氏にとって低山の魅力とは「山」と「人・地域」の関係性の中にあり、「自然」や「文化・歴史」がそれらの関係性を探るヒントとなっている。
「自分が好きな歴史小説に出てきた地域や山を訪れ旅することで、地域のこと、ひいては日本について詳しくなっていく。地域を学んで楽しんだり、日本を面白がるのに最適な手段が登山で、その最高の舞台が低山であると思っているんです」
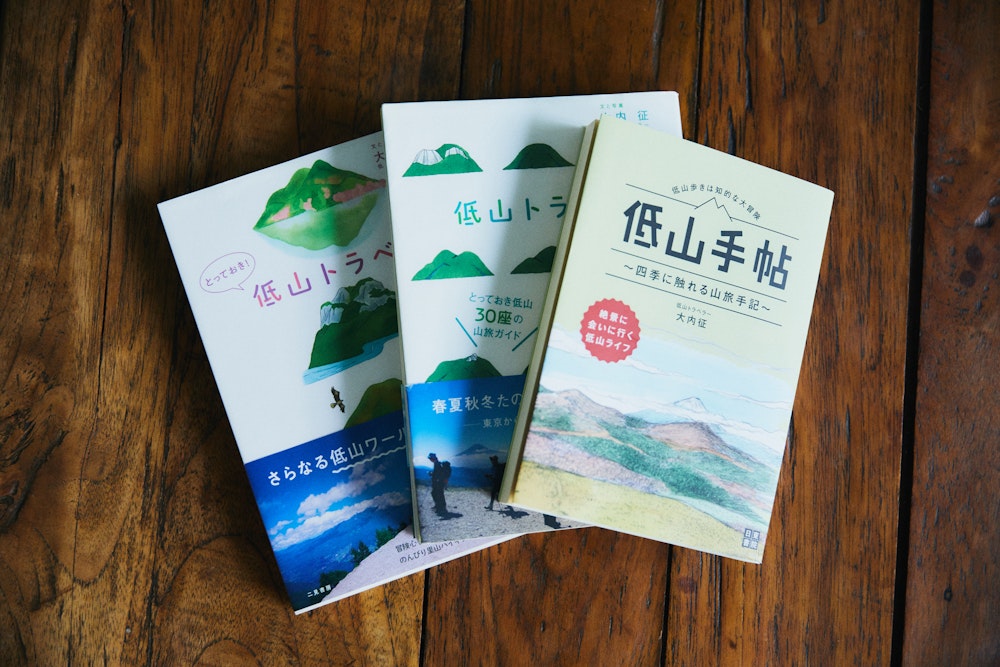
大内氏は、この4月に3冊目の書籍『低山手帖』を出版した。今回の書籍では自らの経験をベースに、より読み物としての充実を図っている。なぜ低山に注目したのか、全国各地の山を歩く中で、どんなことを考えたのかをまとめている。
「日本画家の東山魁夷の絵を見ながら、この舞台はどこだろうと探し歩く登山をしたんです。街中に暮らしている僕らが、自然と触れる最もいい接点のひとつがアートだと考えたからです。はっきり舞台がわかる作品もあれば、千葉の低山の中に新潟の山を描いている、つまり彼の中にある心象風景を描いたものもあることがわかったりしました。そのようなさまざまな発見を本書には盛り込んでいます」
「街」と「自然」。大内氏の話を聞いていると二つのキーワードが浮かんでこないだろうか。一見すると二項対立のようにも見えるが、大内氏自身、過去のインタビューで「憧れの東京に上京して仕事ばかりしていたが、どこかフィットしない感覚があった。都会に合わせようとしていたというか」と語っているように、両者の交わりについて違和感・気づきを得た経験を持っている。そして物語やアートなどからヒントを得て山を巡る中で、両者の繋がりについて思索を積み重ねてきたのではないだろうか。
「『街』と『自然』での体験はどちらが欠けても成立しません。街中で出会った作品や出来事がきっかけで自然の中に繋がっていったり、自然から生まれる恵みや叡智が街の暮らしに活かされたりしています。そういった意味で『街』と『自然』は連続していて、循環している。だからこそ著作や活動の中では、その連続性や循環を体現したり表現したりしたい。街で得たものを山で活かし、山で得たものを街で活かしたいと考えているんです」
「低山トラベラー・文筆家」という独自の肩書きで活動する大内氏のキャリアは、実にオリジナルなものだ。自分なりに描くキャリアの理想があり、作品や人、自然との膨大な触れ合いによって生まれるアウトプットがある。試行錯誤や軌道修正を繰り返しながら独自のルートで登ってきた“山”の先には、何を見すえているのか。その姿を大内氏は以下のように語り、インタビューを締めてくれた。
「今後は、具体的なオーダーがある仕事ではなく、自由度を持って、「あなたらしくやってほしい」と言われるオファーと向き合う時間を増やしていきたいと思っています。私は、オファーの仕事とオーダーの仕事の違いを意識します。オファーは「大内節でぜひやってほしい」と言われてやる仕事のこと。クライアントのオーダーに応えられる実力があってこそのオファーだと思っているので、相手のニーズに応えながらも、「あなたにやってほしい」と言われるような仕事目指しています。
本や講演などを通じて、“低山論”みたいなものを展開してきましたが、今後はより執筆に力を入れ「山旅作家」を目指したい。今は「文筆家」と表現していますが、もっと場数や経験を踏むことで、50歳くらいになった時に「作家」と名乗れるようになりたいです」
Text: Yuka Sato / Photograph: Shunsuke Imai